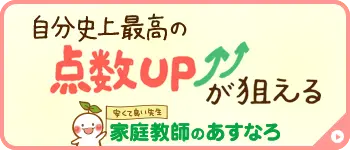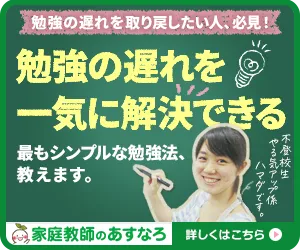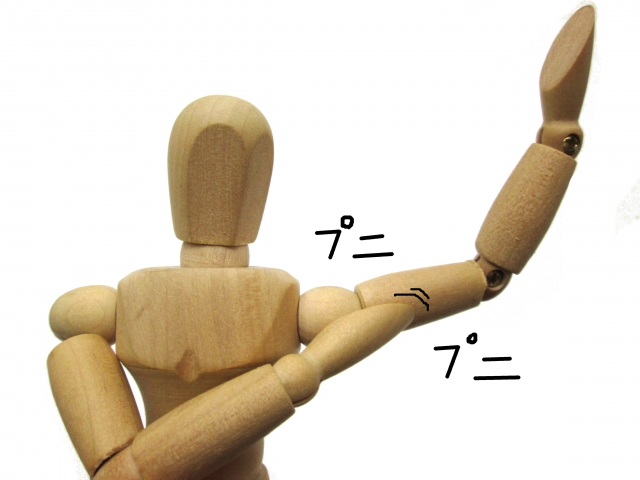【保存版】不登校の子どもが家で穏やかに過ごすための7つの工夫

お子さんが不登校になり、状態が落ちついてくると、親御さんの胸には新たな不安が沸き上がってくるのではないでしょうか?
「うちの子、家ではずっとゲームばかり…」
「このままでいいの?」
「家で何をさせたらいいのかな?」
そこでこの記事では、心の回復と生活リズムを意識した家での過ごし方を7つ紹介します。今日から少しずつ取り入れられる方法をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
『勉強が苦手』な子専門で35年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
不登校の子どもが家で過ごすときに大切な視点とは?
不登校の子どもが家で安心して過ごすためには、「何をすればいいか」よりも、まず「どう関わるか」がとても大切です。
ここでは、子どもの気持ちに寄り添いながら、家庭の中で意識しておきたい基本的な考え方を紹介します。
まずは「安心できる居場所づくり」
子どもが家で安心して過ごせるかどうかは、不登校からの回復にとって最も大切な土台です。
「また怒られるかもしれない」「自分の存在が迷惑なんじゃないか」と感じてしまうと、家にいても心が休まりません。
ですから、
• 勉強しなくても責めない
• ゲームや動画を見ていても、「ダメ!」と頭ごなしに否定しない
• 部屋に閉じこもっていても、無理に引っ張り出さない
といった、 “そのままの子どもを受け入れる姿勢” がとても重要になります。
「無理に元気にならなくてもいいよ」「家ではリラックスしてていいんだよ」
そんな親御さんの声かけと態度で、子どもは安心感を持つことができます。
焦らず、子どもの気持ちを尊重することが大切
「このままずっと学校に行けなかったらどうしよう…」という不安から、つい親は再登校を急かしてしまいがちです。
でも、子ども自身が一番、「このままじゃいけない」と感じているのです。
・朝、今日はどうするの?」と毎日聞かれると、子どもはプレッシャーを感じます。
・兄弟と比較されたり、「昔はあんなに明るかったのに」と言われると、さらに自己否定が強まってしまいます。
代わりに、こう伝えてみましょう。
「行きたくなったらいつでも応援するよ」
「今は心を休める時期なんだよね」
「無理せず、自分のペースで大丈夫だよ」
親御さんとお子さん自身の焦りを抑え、子どものペースを尊重してあげると、少しずつ自分から動き出すエネルギーが生まれくるものです。
「休んでいる=悪いこと」ではないと親が理解する
不登校の子どもは大抵の場合、「学校に行けない自分は、ダメな人間なんだ」と思い込んでしまっています。
学校を休んでいることに対して、強い罪悪感や自己否定を抱えてしまうのです。
そんなとき、親が
• 「早く学校に行きなさい!」と責める
• 「他の子はみんな行ってるのに…」と比べる
• 「将来どうするつもりなの?」と未来を脅す
といった言葉をかけてしまうと、子どもはますます落ち込んでしまいます。
だからこそ、こんな言葉を意識して伝えてみてください。
「体がしんどい時に休むのと同じで、心が疲れたら休んでいいんだよ」
「ちゃんと休めるって、すごく大事なことだよ」
「学校だけがすべてじゃないよ」
親がまず“休んでいること”を肯定してあげましょう。すると、子どもは少しずつ安心し、自分を責める気持ちから解放されていきます。
今日からできる!家でのおすすめの過ごし方7選
家で長い時間を過ごす不登校の子どもにとって、何をして過ごすかは心の回復にも大きく影響します。
そこで、特別な準備をしなくても始められて、子どもの安心感や自信につながる過ごし方を7つご紹介します。
①読書やマンガで心を癒す時間をつくる
本やマンガは、現実のつらさから少しだけ心を離し、安心して別の世界に没頭できる手段です。
文字が苦手な子にはマンガや絵本から始めても大丈夫。図鑑やビジュアルブック、趣味の雑誌などもおすすめです。
• 一緒に図書館や書店に行き、「好きそうな本あるかな?」と気軽に声をかけてみましょう。
• 無理に読ませるのではなく、そばに本を置いておくだけでもOKです。
•
「読書=勉強」ではなく、リラックスのための時間として取り入れてみてください。
②アート・音楽など「表現活動」に触れる
絵を描いたり、音楽を聴いたり、動画をつくったり…。
自分の気持ちをことば以外で表現する「創作活動」は、ストレス発散や感情の整理につながります。
• 100円ショップのスケッチブックや色鉛筆をそっと置いてみる
• ピアノやギターなどの楽器に触れる機会をつくる
• 好きなアーティストのMVを一緒に観る、歌ってみる
•
何かを「作る」「感じる」ことで、言葉にならない思いを少しずつ外に出していくことができます。
③料理や家事を一緒にして自信を育てる
料理や家事は「手を動かしながら成果が見える」活動です。
成功体験をつくりやすく、達成感や役に立っている感覚が得られます。
• 一緒にホットケーキやおにぎりを作ってみる
• 洗濯物をたたんでもらい、「助かるよ、ありがとう」と言う
• お弁当用の卵焼きを作ってもらい、「すごく上手!」と褒める
子どもに任せるときは、「正しさ」よりも「できたこと」に注目して声をかけましょう。
「やってみようかな」という気持ちを大切に育てる関わり方がカギです。
④運動を日課にする(散歩・ストレッチ・体操)
体を動かすと、脳が活性化し、気分が前向きになります。
いきなり外に出るのが難しい場合は、まずは室内で簡単なストレッチから始めましょう。
• 親子で「ラジオ体操」を一緒にやってみる
• YouTubeのヨガ・ストレッチ動画を見ながら一緒にチャレンジ
• 天気が良い日は「近所の公園まで散歩してみない?」と誘ってみる
無理に習慣化させようとせず、「一緒にちょっとだけ」がちょうどいいです。
気分転換としての運動ととらえると無理強いしなくなります。
⑤ゲームやスマホは「時間を区切って」
ゲームやスマホを完全に禁止すると、親子関係が悪化し、余計に依存が強まることもあります。
ですから、「時間を区切る」ことをルール化するほうが、現実的でストレスも少なくすみます。
• 「1時間ゲームしたら、ちょっとストレッチしようね」など、“切り替え”の声かけを工夫する
• タイマーやアプリを使って時間を視覚化する
• 「自分で時間管理する力」を育てる意識を持つ
親子で一緒にルールを考えて、子ども自身に納得感を持たせるようにしましょう。
⑥通信教育・フリースクールを活用するのもアリ
「完全に勉強から離れてしまうのが不安…」という場合は、少しずつ学びに触れられる環境を用意しておくのもひとつの方法です。
• 興味のある教科だけ取り組める通信教材(マンガ形式やゲーム感覚のものも◎)
• Zoomなどで参加できるオンラインフリースクール
• フリースクールの見学だけ、親と一緒に行ってみる
無理に「勉強しなさい」ではなく、「楽しそうなのがあったから一緒に見てみる?」と、きっかけ作りを親がしてあげるイメージでやってみてください。
⑦昼夜逆転を防ぐ工夫(朝日・朝食・軽い活動)
不登校が続くと生活リズムが乱れやすく、昼夜逆転になってしまうケースも多くあります。
体内時計を整えるには、「朝の過ごし方」がポイントです。
• 朝カーテンを開け、日光を浴びる(数分でもOK)
• 「一緒にパン焼こうか」「朝ごはん食べよっか」と誘ってみる
• 起きる時間に合わせて軽く話しかけ、足音を立てて空気を動かす
無理に「起こす」のではなく、自然に生活音の中に招き入れる工夫がおすすめです。
朝の習慣が整ってくると、気持ちも少しずつ整ってくるので、ぜひ実践してみてください。
親ができるサポートと声かけの工夫
子どもを思う気持ちが強いほど、つい口出ししてしまう、先回りして用意してしまう、そんな場合もあるかもしれません。
でも、不登校の子どもには「静かに見守るサポート」が何よりも効果的な対処法です。家庭でできる関わり方や声かけのコツを具体的にお伝えします。
干渉しすぎず、そっと見守る姿勢
親御さんとしては、「何かしてあげたい」「状況を変えたい」と、毎日思って「何かしなくちゃ」とあれこれやろうとしてしまう場合があります。
ですが、過干渉はいけません。
• 「今日は何してたの?」「YouTubeばかり見てるの?」と毎日聞いてしまう
• 「明日は学校行けそう?」と頻繁に確認してしまう
• 「こんな生活、いつまで続けるの?」と不安をぶつけてしまう
…これらの言葉は、子どもにとっては「責められている」言葉そのものです。
代わりに、
• 部屋の前に好きな飲み物をそっと置いておく
• 一緒にテレビを見ながら何気ない会話をする
• 「行ってきます」「おかえり」など、普通の会話を大切にする
など、『干渉せずに関係をつなぐ“間接的な関わり”』 を意識してみましょう。
子どもが話しかけてきたときは、スマホを置いてしっかり目を見て、「うん、そうなんだ」とうなずきながら聞くことが、何よりのサポートになります。
実践していくと体感できますから、今から試してみてください。
「いつでも応援してるよ」と伝える言葉の力
不登校の子どもは、「迷惑をかけてる」「がっかりされてるかも」と思い込み、親に申し訳なさを感じていることが多いです。
また、何も言わなくても、子どもは親の表情や雰囲気から“責められているような気持ち”になることもあります。
ですから、そんな時こそ、
• 「あなたのこと信じてるよ」
• 「どんなあなたでも、大切な存在だよ」
• 「ここにいてくれるだけで嬉しいよ」
といった、“存在そのもの”を肯定する言葉を意識的に伝えてあげましょう。
たとえば、お風呂あがりやご飯の後に、「今日も一緒にご飯食べられて嬉しいな」とポツリと伝えるだけでも、子どもの心は温まります。
「目に見える成長」だけでなく「心の安定」に注目
不登校になると、どうしても「いつ学校に戻れるのか」「このままで大丈夫なのか」と、“わかりやすい成果”を求めてしまいがちです。
でも、本当に大事なのは、子どもが少しずつ自分自身を取り戻していく過程なのです。
たとえば…
• 少しずつ顔つきが穏やかになった
• ご飯を一緒に食べられる日が増えた
• 自分から話しかけてくれるようになった
• 外に少し散歩に出てみようと思えた
こうした変化こそ、子どもが心を回復させている証拠です。
親がその変化に気づき、「最近ちょっと笑顔が増えたね」「おしゃべりできて嬉しい」と声をかけると、子どもは「認めてもらえてる」と感じます。その気持ちが、さらに前に進む原動力になっていくのです。
家での時間が「子どもが安心して回復できる時間」になりますように
不登校は、親にとっても子どもにとっても、不安や戸惑いの連続です。
でも、 「今は休むとき」「家で心を整える時間」 と捉えてみると、見える景色が血が来ます。
• 家の中で少し笑えるようになった
• ご飯を一緒に食べられるようになった
• 朝起きられる日が少しずつ増えた
そんな一つひとつの小さな変化は、子どもが前に進んでいる証です。
親御さんが「大丈夫だよ」「あなたの味方だよ」と伝え続けることで、子どもは自分を少しずつ取り戻していけます。
ですから決して、焦らないでください。安心できる家が、回復の第一歩になり、お子さんは少しずつ前に進んでいくのです。
不登校サポート資料
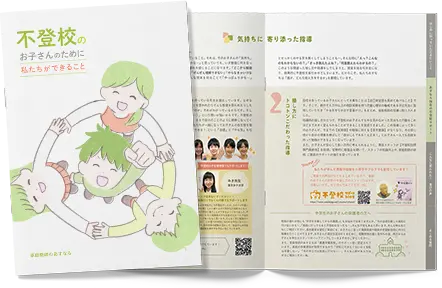
この資料でわかること
- 不登校の心の4つの状態
- 勉強をスタートできるのはいつ?
- 不登校の子におすすめの勉強法 など
不登校でも、勉強の遅れを一気に取り戻せる方法をご紹介!
お子さんが勉強を再スタートするとき手元にあると安心できる!