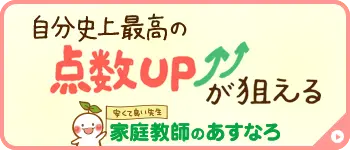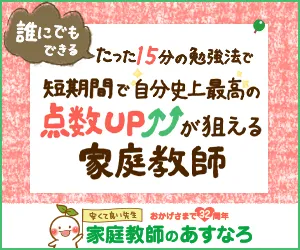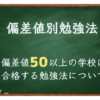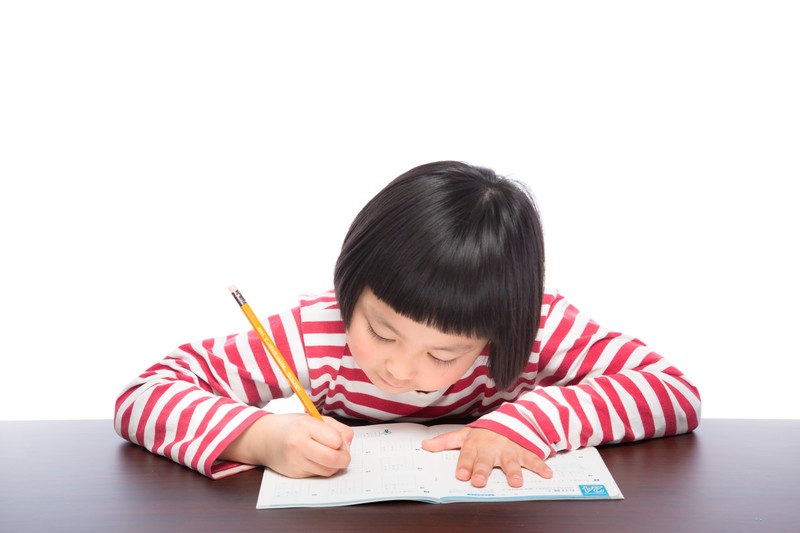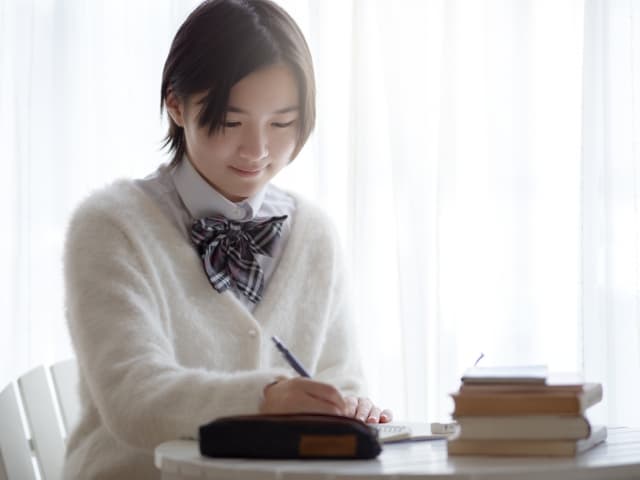高卒認定試験のリアルな難易度と効率的な勉強法、進学・就職への活用法

「高卒認定試験の難易度を知りたい!」
「どれだけ試験勉強をすればいいの?」
「認定資格を取ったあとのキャリアパスにはどんなものがあるんだろう?」
そんな想いを持つ人の背中を押してくれるのが「高卒認定試験」です。
この試験は、文部科学省が実施する国家試験で、高校を卒業していない方が大学や専門学校の受験資格を得るための制度です。
いわゆる「旧・大検」として知られていたもので、合格すれば「高校卒業と同等以上の学力」があるとみなされます。
現在では、学校を中退した方や社会人の学び直し、子育て中の主婦、留学希望者など、幅広い層が受験しています。
本記事では、「高卒認定試験とはそもそも何か?」という基本情報から、科目・出題範囲・難易度、効果的な勉強法、独学とサポートサービスの違い、さらには合格後の進路やよくある誤解まで、トータルでわかりやすく解説していきます。
『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
高卒認定試験とは?
高卒認定試験(旧・大検)は、高等学校を卒業していない人が、大学や短大、専門学校への進学資格を得るために設けられた国家試験です。
合格すれば「高校卒業と同等以上の学力がある」と認められ、受験資格や就職活動にも有利に働く場面があります。
通信制高校や定時制高校に在籍中の生徒、学校を中退した方、社会人の方など、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が受験しています。
高卒認定試験の難易度はどれくらい?
高卒認定試験の難易度は「高校基礎レベル」とされ、しっかりと準備すれば十分に合格可能な試験です。
しかしながら、全科目に一度で合格するには相応の対策が必要です。
ここでは、出題科目や合格基準、科目ごとの難易度や合格率、よくある「簡単すぎ」という声の真偽について、実際のデータや受験者の声を交えて詳しく解説します。
- 科目数・出題範囲・必要な合格点
- 高卒認定試験の合格率は?どの科目が難しい?
- 「簡単すぎ」「ノー勉で受かる」は本当か?
科目数・出題範囲・必要な合格点
高卒認定試験は全8~10科目からなり、必修科目と選択科目に分かれています。
たとえば「国語」「数学」「英語」「世界史AまたはB」などがあり、過去に高校で修得した単位に応じて一部科目が免除されるケースもあります。
出題範囲は高校1~2年程度の基礎学力が中心で、各科目の合格点は100点中40点程度が目安とされています。
40点程度の得点獲得となると、基礎をしっかり押さえていれば十分合格が狙える内容になっているので、大学の入試よりは簡単であるというイメージを持っておくといいでしょう。
高卒認定試験の合格率は?どの科目が難しい?
高卒認定試験の合格率は平均して40〜50%ほどになります。
全科目に一回で合格するのは決して簡単ではありませんが、合格した科目は次回以降も有効です。
科目別に見ると「数学」「英語」「現代社会」などが難易度が高いとされる傾向があります。
これらは過去問で傾向をつかみ、重点的に対策をしておくと安心です。
「簡単すぎ」「ノー勉で受かる」は本当か?
ネット上では「簡単すぎ」「ノー勉で受かった」などの声もありますが、一部の学力が高い受験者のケースです。
基本的には高校基礎レベルの理解と、過去問対策を中心にした準備が合格のカギとなります。
とくに文系科目は暗記中心で対策しやすい一方、理系科目は理解が必要なため、きちんと勉強時間を確保した方が安全に合格できるでしょう。
とはいえ、高卒認定を取得し大学受験をするお子さんであれば、できる限り80点以上の得点を目指し、受験基礎固めができているかを確認してください。
高卒認定試験に受かるための勉強法
高卒認定試験は独学でも合格可能な試験ですが、効率よく対策するには正しい勉強法の理解が不可欠です。
科目数が多いため、各科目に適した学習方法やスケジュールの組み方が合否を分けます。
以下では、独学に適した教材選びや学習手順、さらに予備校・通信講座・家庭教師など外部サービスの活用方法について紹介します。
独学での高卒認定試験対策におすすめの方法
独学での合格も十分可能です。文部科学省が提供している「高卒認定試験学習支援サイト」や、市販の問題集、過去問(5年分以上)を活用することが基本です。
まずは過去問を解き、自分の得意・不得意を把握し、科目ごとに対策を立てましょう。
一部ですが各分野の勉強法の概要は次のとおりです。
| 科目名 | 主な対策法 | ポイント |
|---|---|---|
| 英語 | 文法書+過去問演習+単語暗記 | 基礎文法の習得と単語・熟語の反復が重要 |
| 数学 | 教科書レベルから応用へ段階的に学習 | 解法パターンの習得と出題傾向の分析がカギ |
| 世界史・日本史 | 一問一答+通史本併用 | 流れの理解+知識の積み上げ |
| 科学と人間生活 | 教科書+図解資料+要点暗記 | 図やイラストを活用した視覚的な記憶が有効 |
| 生物基礎 | 教科書+図表中心+頻出問題の暗記 | 視覚情報(イラスト・表)を活かしてインプット |
以下では詳細な勉強法を解説します。
英語の勉強法
英語は基礎文法と語彙力の習得が鍵です。
まずは中学〜高校レベルの文法書を1冊やり切ることが目標です。「時制」「助動詞」「関係詞」など、よく出る文法項目をしっかり理解しましょう。
文法の土台ができたら、過去問に取り組み、頻出の設問形式(整序・語彙選択・文補充など)を把握しておきます。
語彙力は単語帳やアプリを使って毎日こつこつ覚えるのが効果的です。
また、長文読解にも慣れておく必要があり、一文ずつ丁寧に構造を確認しながら読み進め、意味の区切りや文の流れをつかむ練習を積みましょう。
数学の勉強法
数学は分野ごとの「パターン習得」が合格への近道です。
最初は中学レベルの計算問題から始め、一次方程式や比例・反比例などの基本を固めましょう。
その後、高校レベルの関数・図形・確率などに段階的に取り組みます。
重要なのは、間違えた問題をそのままにせず「解き直しノート」を作ること。
どこで間違えたのか、どう解けばよかったのかを整理することで、解法の引き出しが増えていきます。
過去問では「どの分野がよく出るのか」を分析し、頻出単元に絞って重点的に演習するのが効率的です。
世界史・日本史の勉強法
歴史科目は「流れの理解」と「語句の暗記」をバランスよく進めることが重要です。
まずは通史本を読み、時代ごとの大きな流れをつかみましょう。
次に一問一答形式の問題集で、重要語句を徹底的に覚えていきます。
知識が定着してきたら、過去問に取り組み「正誤問題」や「語句選択形式」に慣れることが必要です。
歴史は単なる暗記科目ではなく、因果関係や時代背景を押さえると理解が深まります。
地図や年表、図解資料も活用して視覚的に整理することで、記憶に残りやすくなります。
科学と人間生活の勉強法
「科学と人間生活」は暗記中心ですが、図やイラストを活用することで学習効率が上がります。
人体の仕組み、エネルギーの利用、環境問題など幅広いテーマが出題されるため、単元ごとに要点をまとめて学習するといいでしょう。
資料集や図解入り参考書を使って、視覚情報と一緒に知識をインプットするのが効果的です。
覚えるべき用語や定義は、赤シートや暗記カードなどを使って何度も確認します。
過去問で出題傾向を把握し、よく出る単元を重点的に復習することで、無駄なく得点力を伸ばせます。
生物基礎の勉強法
生物基礎は「図解」と「語句暗記」がポイントとなる科目です。
細胞・遺伝・進化・生態系など、テーマがはっきり分かれているため、単元ごとに区切って学習を進めましょう。
まずは教科書や基礎参考書で全体像をつかみ、イラストや図を使って視覚的に理解するのがおすすめです。
とくに遺伝の分野は頻出なので、遺伝子やDNA、優性・劣性などの概念をしっかり押さえておきましょう。
一問一答やクイズ形式での復習も効果的です。過去問を解いて「よく出る単語・図表」に慣れ、得点源にできるように仕上げていきましょう。
高卒認定試験におすすめの参考書・問題集
高卒認定試験におすすめの参考書や問題集は次のとおりです。
| 教科 | タイトル | 出版社 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 英語 | 『高卒認定 スーパー実戦過去問題 英語』 | 東京学参 | 解説が詳しく、頻出パターンを網羅 |
| 英語 | 『Next Stage 英文法・語法問題』 | 桐原書店 | 文法の基礎固めに最適(高校生向け定番) |
| 数学 | 『チャート式 基礎からの数学Ⅰ+A』 | 数研出版 | 解説が丁寧で初学者向けに最適 |
| 数学 | 『高卒認定試験 過去問題集 数学』 | 成美堂出版 | 問題傾向をつかむのに最適な過去問集 |
| 世界史・日本史 | 『高校とってもやさしい世界史/日本史』 | 旺文社 | 通史をイラスト・図で解説、初心者向け |
| 世界史・日本史 | 『一問一答 世界史B/日本史Bターゲット』 | 山川出版社 | 暗記用に特化した一問一答形式 |
| 科学と人間生活 | 『高卒認定 科学と人間生活 予想問題集』 | 東京学参 | 要点の整理と問題演習が両立できる一冊 |
| 生物基礎 | 『大森徹の 生物基礎 が面白いほどわかる本』 | 中経出版 | 図が多く初心者でも理解しやすい |
| 共通 | 『高卒認定試験 合格テキスト&過去問題集シリーズ(全科目)』 | 成美堂出版/学研 | 各科目ごとに1冊完結で使いやすい |
これらの参考書はあくまでおすすめであって、自身にあった参考書を見つけたり実際に使ってみて使用感を試すことが重要です。
予備校・通信講座・家庭教師の活用とメリット
独学に不安がある方や、確実に短期間で合格したい方は、予備校や通信講座、家庭教師の活用も選択肢になります。
以下に各学習方法をまとめたため、概要を確認してみましょう。
| 項目 | 予備校(通学型) | 通信講座(オンライン・郵送型) | 家庭教師(訪問・オンライン含む) |
|---|---|---|---|
| 学習スタイル | 教室に通って受講。講師が直接指導 | テキスト・動画で自宅学習 | 講師が自宅に訪問またはオンラインで指導 |
| 特徴 | ・集団授業でペースが作れる ・模試や進路指導あり | ・好きな時間に学習可 ・反復しやすい | ・完全個別対応 ・学習計画も管理してもらえる |
| 対象者 | 通学可能な学生/学習習慣を作りたい人 | 忙しい社会人/育児中/マイペースな学習をしたい人 | 自学が苦手/個別指導で力を伸ばしたい人 |
- 模試や進路指導あり ・好きな時間に学習可
- 反復しやすい ・完全個別対応
- 学習計画も管理してもらえる
対象者 通学可能な学生/学習習慣を作りたい人 忙しい社会人/育児中/マイペースな学習をしたい人 自学が苦手/個別指導で力を伸ばしたい人
これらの方法がメインとなるため、自身のライフスタイルにあった方法で、教育サービスを活用してみてください。
高卒認定試験の受験スケジュールと費用
高卒認定試験は年に2回実施され、誰でも受験できる国家試験です。
とはいえ、申込みのタイミングや必要書類、会場選び、試験当日の流れを把握しておかないと、思わぬミスにつながることもあるでしょう。
また、受験料や科目免除制度の仕組みについても事前に知っておくことで、効率的かつ経済的な受験が可能になります。
以下では、試験日程、申込方法、費用と免除制度について詳しく解説します。
年に何回?いつ申し込む?
高卒認定試験は年2回(例年8月と11月)に実施されます。
出願はその約3ヶ月前から始まり、インターネットまたは郵送で申し込みが可能です。
申込書類には受験申請書、写真、身分証明書、前歴を証明する書類(在籍証明書や中退証明など)が必要となる場合があります。
受験会場と試験当日の流れ
試験は全国各地の会場で実施され、希望する地域を選んで申し込みます。
受験票が郵送された後、当日は指定された会場へ。
1日に複数の科目を受験することが可能ですが、時間配分や体力に配慮しながらスケジュールを組むことがポイントです。
筆記用具や昼食、水分補給など、試験に集中できる環境を整えて臨みましょう。
受験費用の目安と科目免除制度
高卒認定試験は、1科目あたり数百円〜千円程度の受験料がかかります(年度によって異なる)。
全科目で数千円〜1万円前後が一般的な費用感です。
また、高校で修得済みの単位があれば、該当科目は免除申請することで受験不要になります。
科目免除には在学中または中退した学校からの証明書類が必要です。
高卒認定試験合格後の進路・可能性
高卒認定試験に合格すれば「大学受験資格」が得られるだけでなく、その後のキャリアの選択肢が大きく広がります。
近年では、学び直しを目的とした社会人や子育て中の主婦が高卒認定を経て進学するケースも増えており、自由なライフスタイルを実現する手段のひとつとして注目されています。
以下では、大学進学・専門学校進学・就職・転職など、合格後にどのような道が開かれるのかを具体的に紹介します。
進学と就職のハイブリッドを目指す人も増加中
高卒認定試験に合格した後の進路は多様化しています。大学や専門学校への進学はもちろん、フリーランスや企業就職、起業を目指す人もいます。
また、高卒認定を取得しながらアルバイトや派遣で社会経験を積むスタイルも広がっており、「学び直し」や「キャリアチェンジ」の手段としても活用されています。
とくに通信制大学や夜間大学など、柔軟な学び方と組み合わせて人生設計を描く人が増えています。
高卒認定試験は意味ない?よくある誤解と真実
「高卒認定なんて意味ない」「ずるい」といった誤解や偏見が、いまだに一部で見られます。
しかし実際には、制度としての信頼性は高く、合格者は進学・就職などで確実にチャンスを掴んでいます。
以下では、よくある批判や否定的な意見に対する根拠ある反論を提示し、合格後に後悔しないための心構えや、制度の意義を正しく理解するための視点をお伝えします。
「意味ない」「ずるい」と言われる理由と反論
「高卒認定なんて意味がない」「高校をきちんと卒業してないからずるい」など、心ない言葉を投げかけられることもあるかもしれません。
しかし、高卒認定は文部科学省が正式に認定する制度であり、進学・就職の実績も十分あります。
自分の選択に自信を持ち、批判に惑わされず進むことが重要です。
合格しても後悔するケースとは?
一方で「合格しても大学に行かなかった」「進路を明確に決めないまま取得してしまった」という後悔の声もあります。
こうした失敗を避けるためには、合格後の目標や行動計画を早い段階で考えておくことが大切です。
試験合格はゴールではなく、あくまでスタート地点という認識を持ちましょう。
高卒認定試験は「人生を変える手段」になり得る
高卒認定試験は、自分の将来を切り開くための「選択肢の一つ」であり、「人生を変えるきっかけ」ともなり得ます。
中卒や高校中退でも、自らの努力で進学や就職の道を切り開くことができるという強いメッセージが込められた制度です。
現状に悩みや不安がある方こそ、前向きに検討してみる価値があります。
高卒認定試験の難易度まとめ
高卒認定試験は、努力すれば誰でも合格を目指せる現実的な試験です。
出題範囲も広すぎず、科目免除や自分の得意分野を活かした対策ができるため、効率よく進めることが可能です。
「高校を卒業していない=終わり」ではなく、「これから再スタートを切れる機会」として、本試験を積極的に活用しましょう。
進学・就職・キャリアアップなど、あなたの未来を切り拓く一歩として、高卒認定試験は強力な選択肢になり得ます。
お子さんの勉強でお困りのお母さんへ
- ゲームやYouTubeばっかりで全然勉強しない
- 勉強のやり方がわかってない
- テストではいつも平均点以下…
- 塾に行っても、なかなか結果が出ない
- 通信教材も三日坊主。どんどん溜まっちゃう
- 不登校や発達障害で勉強が遅れている
そんなお子さんの状況なら『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。