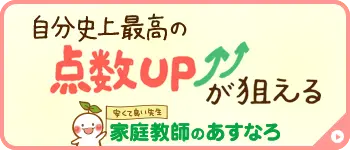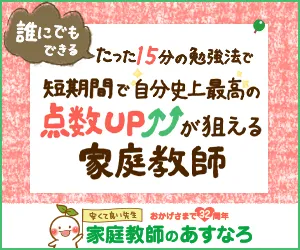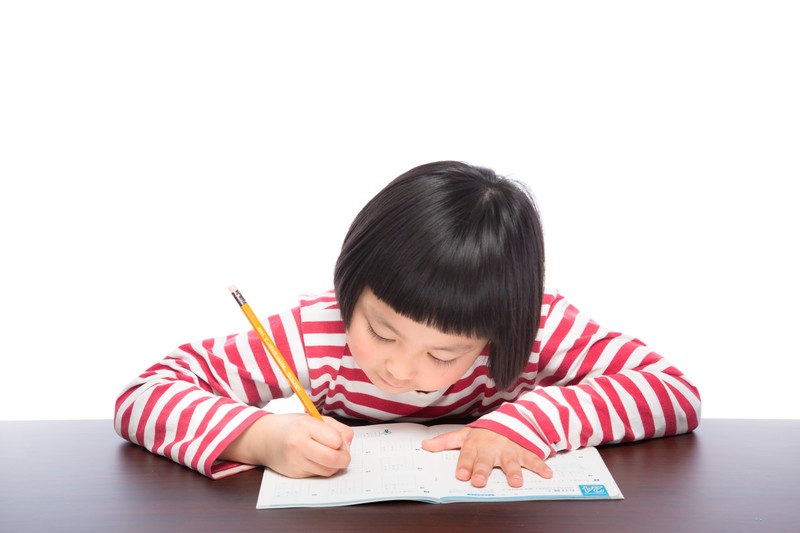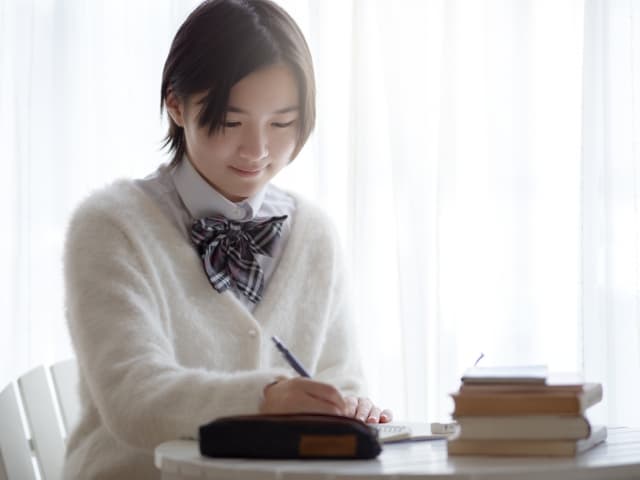【最新版】成績アップしたいなら朝勉強!効率が上がる時間帯と理由

「うちの子、こんなに勉強しているのに、なんで結果が出ないの?」
そんなふうに悩んでいませんか?
実は、脳の働きや集中力には“ゴールデンタイム”があります。ですから、勉強は、する時間帯によって効率が大きく変わってしまいます。
やみくもに長時間勉強するだけでは、時間の無駄になってしまうことも…。
ですが、逆に、時間帯で変わる脳の働きに合わせて学習内容を工夫すれば、今よりもっとカンタンに成績アップを目指せるってことなんです!
そこでこの記事では、勉強効率が最も上がる時間帯や、【時間帯別の効果的な勉強法】を具体的にわかりやすく解説します。
何をやっても点数アップが難しいと感じているなら、ぜひ、やってみてください!
『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
朝・昼・夜どの時間に何をする?時間帯ごとの具体的勉強例
「成績が伸びる子は、勉強する時間帯にも工夫がある」と言われていることをご存じですか?それは、脳の働き方が時間帯によって変わるからです。
以下では、【朝・昼・夜】それぞれに適した学習内容を紹介していきます。
【朝】インプット学習に最適
朝は、脳が最もクリアな状態で、集中力や吸収力が高まっている時間帯です。
睡眠中に脳内の情報が整理されるため、朝は頭がリセットされ、新しい知識を効率よくインプットできるゴールデンタイムといわれています。
短時間でもコツコツ続けていくと、暗記も簡単にできて理解力も深まり、成績アップにつながります。
特に、計算や英単語、漢字など反復練習が必要な内容は、朝に取り組むと効果的です。
さらに、朝の勉強習慣があると、その後の学校生活にもよいリズムが生まれるので、学習意欲や集中力がグンと向上していきます。
<朝におすすめの勉強内容>
・英単語や漢字の暗記
・計算ドリル(数学・算数)
・理科・社会の用語暗記
・音読(国語・英語教科書)
・前日の復習やテスト直し
【昼】理解・応用・アウトプットに向いている
昼間は、脳がしっかりと目覚め、活発に働いている時間帯です。
午前中にインプットした知識を整理して、実際に問題を解いてアウトプットすることで、理解が深まりやすくなります。
学校から帰ってきた後や、休日の昼間は、集中力や思考力が安定しやすい時間帯でもあるため、難易度の高い問題演習や、応用力を養う学習に取り組むのがおすすめです。
また、過去問や実戦的な問題を解くことで、自分の理解不足や弱点が見えやすくなり、効率よく対策を進めることができます。
<昼におすすめの勉強内容>
・学校の課題・宿題
・問題集での反復演習(英語・数学・理科など)
・過去問演習(受験生)
・読解問題(国語・英語長文)
・ノートまとめや解説確認
【夜】暗記・復習・翌日の準備に向いている
夜は、一日の学習内容を整理し、記憶を定着させるのに適した時間帯です。
人間の脳は、眠っている間にその日に得た情報を整理し、必要なものを長期記憶として保存する働きがあります。
そのため、寝る前に暗記した内容は、翌朝に思い出しやすく、テストや実践で活かしやすくなります。
また、翌日の授業に備えて予習や準備をしておくことで、学校での理解度もアップし、成績向上につながります。
とは言え、夜は遅くまで詰め込みすぎず、「軽い復習・暗記・準備」にとどめ、しっかり睡眠時間を確保し、身体の健全さを保ちましょう。それも成績アップの近道です。
<夜におすすめの勉強内容>
・英単語や漢字、社会などの暗記
・理科・社会の用語確認
・翌日の授業予習(範囲確認・下読み)
・間違えた問題の復習・ノート整理
・提出物や翌日の持ち物確認
勉強する時間帯を工夫すると、成績が上がる3つの理由
この項目では、なぜ勉強時間を意識するだけで成績アップにつながるのか、3つの視点から具体的に説明していきます。
脳や体には一日の中で集中しやすいタイミング、疲れやすいタイミングがあります。
そのリズムに合わせて学習を工夫すれば、 「同じ時間勉強しても、結果が出やすい」 「無駄なく効率的に覚えられる」 といった効果が期待できます。
その理由を知って、ぜひこれからの学習計画に活かし、点数アップを狙ってください!
脳のゴールデンタイムを活かす
脳には、一日のうちで働きやすい時間帯があります。
特に、朝から昼にかけては記憶力・集中力・理解力が自然と高まりやすい時間帯といわれているので、この時間帯を活かして学習すると、短い時間でも効率よく成果を出せます。
たとえば、午前中に新しい知識を学び、午後に応用問題に取り組むという流れを作れば、知識がしっかり定着しやすくなります。
時間帯に合った勉強を意識することが、ムダな勉強時間を減らし、成績アップへの近道になると言えます。
集中力と作業効率が変わる理由
集中力には、人それぞれリズムがあります。
ですが、ほとんどの人に共通しているのは、「疲れているとき」「眠いとき」には集中できないということ。
疲れや眠気を感じやすい夜に長時間机に向かうより、集中できる時間に必要な学習をサッと終わらせた方が、結果的に効率も点数もアップします。
また、「集中できる時間」を知っていると、ダラダラと長時間勉強する必要がなくなります。短い時間でも成果が出やすくなるので、お子さんも達成感を得やすいですし、学習への前向きな気持ちも育ちます。
生活リズムと成績の関係
生活リズムの乱れは、勉強の集中力や理解力を大きく左右します。
なぜなら、夜更かしや睡眠不足が続くと、脳がスッキリ働かず、学習効率も下がってしまうからです。
反対に、毎日決まった時間に寝起きし、一定のリズムで学習することが習慣になれば、自然と集中力が高まり、勉強の質も安定します。
生活リズムが整うと、脳も体も学習しやすい状態を保ちやすいので、成績向上につながる良い循環が生まれていきます。
学年別|おすすめ勉強時間帯の活用法
学年や成長段階によって、効果的な勉強時間帯や、勉強スタイルは変わってきます。
年齢が低いほど集中できる時間は短く、学年が上がるごとに、学習内容や目的に合わせた時間帯の使い方が重要になります。
そこで、小学生から高校3年生まで、それぞれの学年に合った効果的な時間帯活用法を具体的に解説します。
小学生・中学受験の場合
小学生は、長時間集中するのが難しい時期。
特に低学年は、学校から帰宅後すぐの短時間学習が効果的です。夜遅くまで机に向かう必要はありません。
中学受験を控えている高学年は、夕方に学校課題を終え、夜は軽い暗記や復習で記憶を定着させるとよいでしょう。ただし、成長期ですから、睡眠時間を削らないことが重要です。
中学1〜2年生
この時期は、勉強習慣をしっかり身につけることが最優先。
夜遅くまでの詰め込み学習は逆効果なので、夕方〜夜に1〜2時間を目安に集中して勉強する習慣をつけましょう。
学校から帰宅後、すぐに宿題や予習復習に取り組むと、生活リズムが整い、安定した学力アップにつながります。
中学3年生
受験が近づき、計画的な学習が必要になる時期です。
夜遅くまで詰め込みすぎるのではなく、朝・昼・夜それぞれ時間帯ごとに役割を分けて勉強するスタイルがおすすめです。
朝:短時間で暗記や英単語、漢字
昼:学校授業や演習問題
夜:その日の復習、間違えた問題のやり直し、翌日の準備
夜は軽めの復習にとどめ、睡眠を削らずコンディションを保つことが受験成功のカギです。
高校1〜2年生
高校1・2年生は、定期テストや模試に向け、日々の学習習慣を安定させる時期。
この時期は、夜遅くまで勉強するより、生活リズムを整えて「朝・昼・夜」のバランスを意識した学習が効果的です。
朝:短時間で英単語や計算練習
昼:学校の授業+課題・問題演習
夜:復習・応用問題・苦手科目の克服
部活などで帰宅が遅い場合でも、夜は「ダラダラ長時間」ではなく、メリハリをつけた勉強を心がけましょう。
受験生(特に高校3年生)
高校3年生は、受験を見据えて自分に合った「時間帯の使い方」を確立することが大切です。
夜遅くまで無理に勉強するよりも、朝から学習リズムを整え、集中できる時間帯をフル活用するのが合格への近道と言えます。
朝:脳を活性化する暗記・計算練習(英単語・漢字・数学)
昼:授業+応用問題、過去問演習
夜:その日の復習・弱点克服・翌日の準備
受験直前期は、夜型生活にならないよう注意し、本番当日の時間帯に集中力が発揮できる生活リズムを意識してください。
時間帯だけじゃない!成績アップには「集中できる環境」が必須
いくら勉強時間帯を工夫しても、集中できない環境では効果は半減してしまいます。ですが、集中できる環境さえ整えば、短時間でも質の高い勉強ができるようになります。
これは子どもの成績アップに直結する、大切なポイントです。
ここでは、親御さんが家庭で取り入れやすい具体的な対策をご紹介しますので、ぜひ、お子さんに合ったやり方を見つけてください。
スマホ・ゲームなど「集中を妨げるもの」を遠ざける
・勉強中はスマホを親に預ける(目に入るだけで集中力が削がれる)
・ゲーム機・タブレットは視界に入らない場所へ片付ける
・机の上は、必要な教科書と筆記用具だけ
▶ 「スマホ=集中力の敵」とルール化することが効果的。
短時間でも集中できる環境をつくりましょう。
集中できる学習場所を整える
・静かな部屋(テレビ・音楽・話し声がない場所)を選ぶ
・机や椅子の高さを体に合ったものに調整
・照明は暗すぎず明るすぎず、目に優しいものに
▶ 環境が整っていないと、子どもはすぐに姿勢が崩れ、集中が切れてしまいます。
集中できる「学習専用スペース」を用意してあげましょう。
「短時間集中→休憩」で集中力を維持する
・ポモドーロ法(25分集中+5分休憩)を取り入れる
・時間を区切って勉強、タイマーで管理する
・休憩中は立ち上がってストレッチや水分補給をする
▶ 長時間ダラダラより、短時間でも集中できる時間を区切った方が効果的。
休憩を挟むことで、疲れずに勉強の質が保てます。
勉強開始前に「ToDoリスト」で頭を整理
・今日やるべき課題を紙に書き出す(3つ以内がベスト)
・「英単語30個」「数学問題3ページ」「理科復習1時間」など具体的に
・終わったら線で消すことで達成感を得る
▶ 目的が曖昧なままだと、子どもは集中しづらいもの。
やるべきことを明確にしてから取り組むことで、集中力が続きます。
家族が協力して、静かな時間を作る
・夕方〜夜の勉強時間は、家族も静かに過ごす意識を持つ
・兄弟がいる場合は別室で遊ばせる、テレビの音量を下げる
・「今は勉強タイム」と家族で共有する
▶ 周囲が協力してくれるという事実があると、子ども自身も、自然と勉強に集中できるようになります。
自分に合う時間帯と環境で、効率よく成績アップを目指そう!
勉強の成果は、「どれだけ長く机に向かったか」よりも、「どれだけ集中して取り組めたか」で決まります。
そのためには、時間帯ごとに脳の働きを意識して、学習内容をうまく使い分ける工夫が大切です。
また、どんなに効果的な時間帯でも、集中できない環境では効果は半減してしまいます。
時間帯の工夫+集中しやすい環境づくり、これが成績アップの近道です。
■ この記事のポイントまとめ
✔ 朝は暗記やインプット系、昼は演習・アウトプット、夜は復習に向いている
✔ 学年ごとにおすすめの時間帯・学習内容は異なる
✔ スマホ・ゲームは遠ざけ、静かで集中できる環境を整える
✔ 短時間集中&休憩のリズムを意識すると効果的
お子さんに合った方法を取り入れながら、効率よく・無理なく学習を続けることで、確実に成績は伸びていきます。
ぜひ今日から、できることから始めてみてください。
お子さんの勉強でお困りのお母さんへ
- ゲームやYouTubeばっかりで全然勉強しない
- 勉強のやり方がわかってない
- テストではいつも平均点以下…
- 塾に行っても、なかなか結果が出ない
- 通信教材も三日坊主。どんどん溜まっちゃう
- 不登校や発達障害で勉強が遅れている
そんなお子さんの状況なら『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。