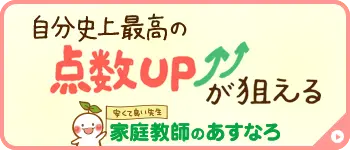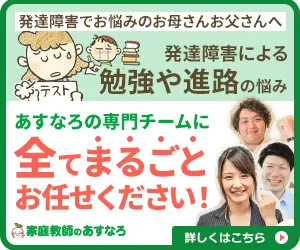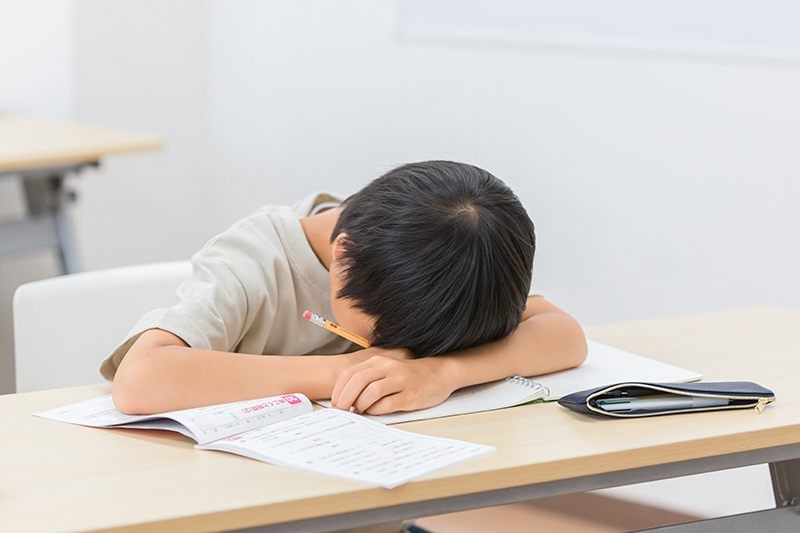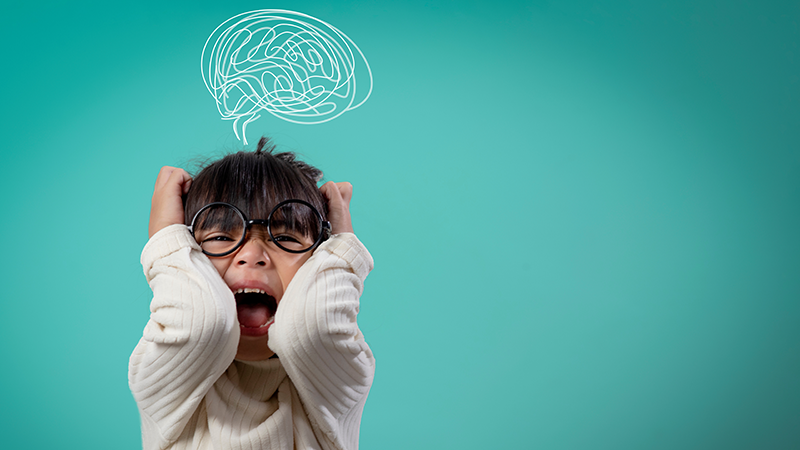WISC-Ⅴ「視空間」とは?VSIが低い時の困り事とサポート方法

「地図が読めない」
「片付けや整理整頓がうまくいかない」
「歩いていると周りの物にぶつかりやすい、つまずきやすい」
「絵を描くのが苦手」
「図やグラフの読み取りに時間がかかる」
お子さんにこんな様子が見られるとき、もしかすると視空間指標(VSI)が関係しているかもしれません。
WISC-Ⅴでは、これまで「知覚推理」としてまとめられていた能力が「視空間」と「流動性推理」に分かれ、それぞれをより詳しく評価できるようになりました。その中でも視空間指標(VSI)は、空間を把握したり、図形を頭の中で操作したりする力を表すものです。
今回は、この視空間指標(VSI)が具体的にどんな力なのか、数値が低いとどんな困りごとが起きやすいのか、そして家庭でできる具体的な支援方法まで、わかりやすく解説していきます。
『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
WISC-Vの視空間指標(VSI)とは?
視空間指標(VSI)とは、見た情報を「形」「向き」「位置」などのイメージとして理解する力のことです。図形の特徴をつかんだり、物の位置関係を把握したり、頭の中で形を動かして考える力がここに含まれます。
この力は、
- 図形やグラフの読み取り
- 展開図や立体の理解
- 地図を読む
- 片付けや位置の把握
など、勉強にも日常生活にも深く関わっています。
視空間指標(VSI)はどんな検査?
WISC-Vでは視空間指標の力を見るために、「積木模様」と「パズル」 の2つの課題が使われます。
積木模様(Block Design)
提示された見本の図形と同じ模様を、色のついた小さなブロックを並べて作るテストです。
この検査では、
- 形の特徴を正しくつかむ力
- 模様のどこをどう見るべきか判断する力
- その形を手を使って再現する力
といった、視覚と空間の理解に必要な力が試されます。
■検査例
見本に「しま模様の正方形」が出されたら、ブロックをどう動かせば同じ模様になるか考えて並べていきます。模様や色の位置をよく観察することがポイントです。
パズル(Visual Puzzles)
こちらは、いくつかのパーツを見ながら、「どの組み合わせで見本の形ができるか」 を頭の中で考えるテストです。
求められる力は、
- 部分と全体の関係を理解する力
- 形を頭の中で回したり、組み合わせたりする力(イメージ操作)
- 必要なパーツを素早く選び出す力
などです。
■検査例
三角形や四角形のパーツを見て、「どのピースをどう組み合わせたら、この見本の形になるのか?」をイメージして答えを選びます。
視空間指標(VSI)から何が分かるの?
視空間指標(VSI)を見ると、こんな「得意・苦手」が分かります。
① 図形や空間を理解する力
展開図・立体・地図など、形や位置関係を扱うときの理解度。
② 見た情報を整理するスピード
どこに注目すればいいか、どの形が正しいかを見分ける速さ。
③ イメージで考える力
頭の中で図形を動かしたり、組み合わせを考えたりする力。
④ 生活面での空間把握
- よくぶつかる
- 距離感がつかみにくい
- 片付けが苦手
といった日常の困りごとも、この力と関係することがあります。
視空間指標(VSI)の数値が高い子どもの特徴
視空間指標(VSI)が高いお子さんは、「見て理解する」「頭の中で形をイメージする」ことが得意なタイプです。
次のような特徴が見られることがあります。
● 図形や空間の理解が早い
立体・展開図・角度など、形を扱う問題の理解がスムーズです。
● パズルやブロック遊びが好き
どんな形ができるか想像したり、組み合わせを考えたりする遊びに強さを発揮します。
● 地図や位置関係の把握が得意
目的地までの道のりや、物の位置関係を理解することに抵抗が少ない傾向があります。
● 手を使った作業が上手
折り紙・模型作り・レゴなど、立体的な構造を考える作業が得意なことも。
● 動きのイメージがしやすい
ダンスの振り付けやスポーツの動きを、見て再現しやすいタイプもいます。
VSIが高いということは、「視覚イメージが理解の中心にある学び方が得意」ということ。この強みは、学習にも日常にも活かすことができます。
視空間指標(VSI)の数値が低い子のよくある困りごと
VSIの数値が低いお子さんは、形・位置・距離感などの「空間的な情報」の処理がやや負担になりやすい傾向があります。
ここでは、日常と学習に分けて具体的に紹介します。
日常生活編
① よくぶつかる・距離感がつかみにくい
机や壁、友達にぶつかりやすかったり、狭いところを通るのが苦手なことがあります。
「どれくらい離れているか」を感覚でつかみにくいためです。
② 片付けや整理整頓が難しい
物の位置関係やどこに置くと使いやすいかがイメージしにくく、片付けに時間がかかったり、散らかりやすくなりがちです。
③ 衣服の前後・裏表を間違えやすい
洋服をひっくり返したときに「どちらが前?」と迷ったり、靴を左右逆に履いてしまうことがあります。
④ 図形やイラストを写すのが苦手
絵を描くときに形が歪んだり、模写がうまくいかないことがあります。見たものを「そのまま頭にとどめて再現する」負担が大きいためです。
⑤ 空間での動作がぎこちない
跳び箱や縄跳び、ダンスなど「動きの位置関係」をとらえる場面が苦手に感じやすくなります。
学習編
① 図形問題が極端にむずかしく感じる
展開図、立体、角度など、空間をイメージする必要がある問題でつまずきやすい傾向があります。
② グラフ・表・地図の読み取りに時間がかかる
どこを見ればいいか分からなかったり、情報を整理するのに負荷がかかりやすいです。
③ 書いたものがずれやすい(マスに収まらない)
ノートのマスの中心に書くのが難しかったり、文字の大きさが安定しないことがあります。
④ 手順をまとめて理解するのが苦手
複数の情報を同時に処理しにくいため、数学の式変形や図形の作図など「ステップの多い作業」で混乱しやすくなります。
⑤ 見て真似する作業がむずかしい
黒板の図を写す、先生の手本を見て工作する、といった場面で時間がかかることがあります。
視空間指標(VSI)の数値が低い子のサポート方法
VSIが低めのお子さんは、「見ればわかるでしょ?」と周りが思うような場面でも、実は情報量が多すぎて混乱してしまっていることがよくあります。
ここでは、日常生活と学習場面に分けて、学校・家庭でできるサポートを紹介します。
日常生活編
① 視覚情報は「シンプル+言葉で補う」
- イラストや図、マークはできるだけシンプルに
- ごちゃごちゃしたデザインより、はっきりした線・見やすい色合いにする
そのうえで、
「ここが朝の支度セットだよ」
「この写真の順番で片付けようね」
というように、言葉で補足してあげると理解しやすくなります。
② 片付け・探し物は「視覚的な構造化」で支える
- よく使う物どうしを同じ場所にまとめる
- ラベルや色を決めておく(例:文房具は青、学校関連は緑 など)
- 片付け完了の状態を写真に撮り、その写真を目印として貼っておく
こうした「見れば、どこに何があるか分かる仕組み」は、
片付けが苦手なお子さんの大きな助けになります。
③ 一度にたくさん言わない・見せない
VSIが低い子は、一度に多くの視覚情報が入ってくると混乱しやすい傾向があります。
- やることリストは「1枚に全部」ではなく、付せんに1つずつ書く
- 終わったら、はがしていく
- 写真カードやイラストも、今必要なものだけを見せる
このように「ひとつずつ」提示することで、見通しが立ちやすくなります。
④ 手順を「見える形」にしておく
- 朝の支度の流れを写真カードで並べておく
- 帰宅後の流れ(手洗い→ランドセル→宿題…)をイラストで示す
など、行動の順番を視覚的に示すと、毎回ゼロから考えなくてよくなり、失敗経験も減っていきます。
学習編
① 視覚情報を整理して「どこを見るか」をはっきりさせる
図・表・グラフ・文章を読むときは、情報を整理してあげることが大切です。
- 重要なところだけ色ペンで線を引く
- 見る順番を番号で示す(グラフだったら①X軸(横軸)→②Y軸(縦軸)など)
- 「まずここだけ見るよ」「次はここね」と視線の誘導をする
例えば英語文なら、主語と動詞に赤線…というように色分けして、「今は赤いところだけ見ようね」と焦点を絞ってあげると、頭の中で処理しやすくなります。
② 情報をひとつずつ処理できるようにする
- 問題文全部を一気に読ませるのではなく、1文ごとに区切る
- 図形の問題も、①線を引く → ②印をつける → ③角度を書く…と分けて指示する
「全部いっぺんに理解してね」ではなく、小さなステップに分けて考えられるようにすることがポイントです。
④ 板書・ノートは「補助ツール」で負担を減らす
- サンプルノートを見せて、どんなレイアウトで写せばいいか示す
- 必要に応じて、板書内容を印刷したプリントを配る
- 写真撮影を許可し、「あとで一緒に整理しようね」と安心させる
「書き写すこと」にエネルギーを使いすぎると、中身の理解に使える力が残らなくなってしまいます。板書やノートについての支援は、ズルではなく大事な合理的配慮です。
⑤ 表現方法を切り替えて、理解の入り口を増やす
- 口頭説明だけでなく、ジェスチャー・実物・絵を組み合わせる
- 言語理解が強い子には、図だけでなく言葉での説明を厚めにする
「視覚情報+言葉+実物」など、複数のチャンネルから情報が入るようにすることで、理解しやすい形を見つけてあげることができます。
視空間指標(VSI)の伸ばし方
視空間指標(VSI)は「見たものを理解する力」「形や位置をイメージする力」のため、
体験しながら育てる方法がとても効果的です。
WISC-VのVSIが低めだったとしても、日常の遊びや活動の中で自然に伸ばしていくことは十分可能です。ここでは、お家でも学校でも取り入れやすい方法を紹介します。
① パズル遊びで「形のパターン」をつかむ力を伸ばす
パズルは視空間能力を育てるための代表的なトレーニングです。
● ジグソーパズル
ピースの向きを考えたり、全体の中でどこに入るか探すことで、形の特徴を捉える力が育ちます。
● 3Dパズル(ルービックキューブなど)
回転・移動・位置の感覚が必要になるため、立体認知が自然に鍛えられます。
② ブロック遊びで「空間の構造を理解する力」を育てる
レゴやナノブロック、積み木、プラモデルなどの“組み立て遊び”は、VSIを伸ばすのに非常に効果的です。
● 見本のモデルを作る
レゴの説明書やプラモデルの組み立て図を見ながら、同じものを作る活動です。
「図を読み取る → 必要なパーツを探す → 同じ形を再現する」という一連の流れが、空間認知を自然に鍛えます。
● パターンを再現する遊び
積み木で見本の形(階段、L字、タワーなど)をそのまま真似して作る遊びです。
色や形、並びを観察しながら配置することで、位置関係をつかむ練習になります。
③ 図形描写・アートで「形を扱う力」をやさしく強化
絵を描いたり図形を写したりする作業は、形の特徴を丁寧に見る練習になります。
● 模写やトレース
好きなキャラクター、アイコン、シンプルな図形などを見本にして模写したり、トレーシングペーパーでなぞったりするだけでも「形を見る力」「線を再現する力」が育ちます。
● コラージュやデザイン
色紙を「丸・三角・四角」などいくつかの形に切って、家・魚・ロボット・花など、ひとつの絵を作るように組み合わせて貼る活動です。
パーツの位置や並び方を考えることで、空間のバランス感覚が自然に鍛えられます。
④ 日常生活の中でもVSIは伸ばせる!
生活の中にも視空間機能を使う場面がたくさんあります。
● 料理
切り方・配置・盛り付けなど、実は空間認知の宝庫です。お母さんが切ったお手本と同じくらいの大きさで切ってね、や、完成写真みたいに盛り付けてね、など、お子さんの手を借りながら楽しくトレーニングできます。
● 地図を読む
家から公園までの道を一緒に地図で確認してから歩く、という経験も良いトレーニングになります。
● 工作
ハサミ・のり・折り紙など、手で形を扱う活動は空間イメージ力を育てます。
⑤ 視覚認知ゲームで「探す力」「パターン認識」を鍛える
● 神経衰弱
視覚記憶や位置の把握が必要になります。
● 探し絵・ウォーリーを探せ
「似ているけれど違うものを見分ける」視覚探査能力が伸びます。
⑥ 体育・ダンスなど身体を動かす活動も効果的
VSIは「目」と「体の動き」が連動することで育つ力でもあります。
● 球技
ボールの軌道を予測する力は空間認知に直結します。
● ダンス・体操
動きの順序や位置関係を理解する必要があり、イメージ力を養います。
⑦ ビジョントレーニングで「見る力そのもの」を底上げする
視空間指標(VSI)を伸ばすうえで欠かせないのが、「見る力」そのものを育てるビジョントレーニングです。
ここでいう「見る」とは、単に視力だけの話ではありません。
● ビジョントレーニングにおける「見る」とは
② 脳でその情報を理解する(視覚認知)
③ 動作や言葉で表現する(アウトプット)
この ①〜③ がスムーズにつながっている状態を育てることが、ビジョントレーニングの目的です。
家庭でできるビジョントレーニング5選
① けん玉
玉の動きを目で追いながらキャッチすることで、動体視力・空間認知・集中力が鍛えられます。ゲーム感覚で取り組めるのがポイント。
② かるた
読み札を聞いて素早く絵札を探すことで、瞬時の判断力・視覚処理・反射的な動きが育ちます。競争形式にすると集中力UP。
③ ティッシュキャッチ
落ちてくるティッシュをキャッチするだけの簡単な遊び。不規則な動きを追うため、動体視力・反射神経を鍛えられます。
④ 色探しゲーム
「赤い物を探して!」など身の回りから色を素早く見つける遊び。観察力・注意力・視覚情報の取捨選択を育てます。
⑤ まねっこゲーム
相手の動きをよく見て真似することで、見た情報を体の動きに変換する力が身につきます。スピードを上げて難易度調整も可能。
まとめ
視空間指標(VSI)が低いお子さんは、図形・地図・グラフの理解、運動での距離感、片付けや手元の作業など、学校生活や日常のさまざまな場面でつまずきを感じやすい傾向があります。
でもその背景には、「見えた情報をどう整理するか」「どう理解するか」 の特徴があるだけで、決して できない子 という意味ではありません。
大切なのは、その子の「見え方」「理解の仕方」に合った環境やサポートを用意してあげることです。
視覚情報をシンプルにしたり、手順をひとつずつ分けて伝えたり、実際に手を動かして体験できる機会を増やしたり…。そうした小さな工夫が、お子さんの安心と自信につながっていきます。
ブロック・図形遊び・ビジョントレーニングなど、楽しみながら視空間の力を高められる方法もたくさんあります。無理のない形で、できることから日常生活に少しずつ取り入れてみてくださいね。
発達障害サポート資料
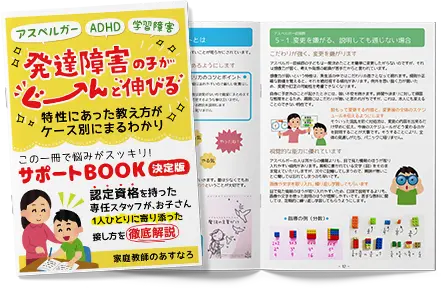
この資料でわかること
- 発達障害の子を伸ばす教育とは?
- 特性に合わせた具体的な教え方
- よくある困りごとと対応例 など
発達障害の専門家が監修!お子さんをぐーんと伸ばす接し方を徹底解説
この一冊で、特性ごとの勉強の悩みがスッキリ解消!
教え方に困った時にスグに対応できる!