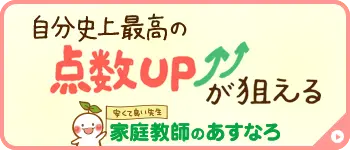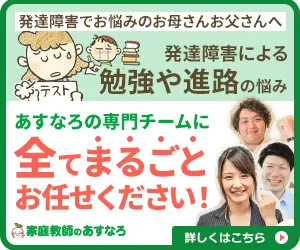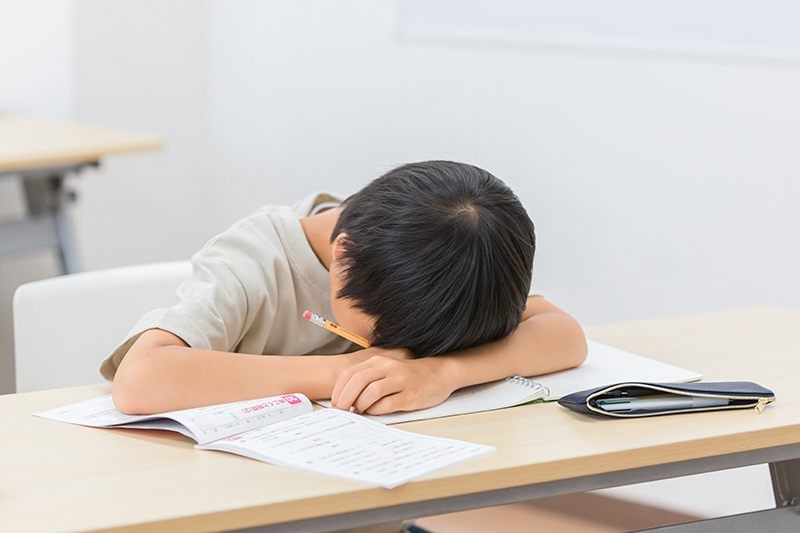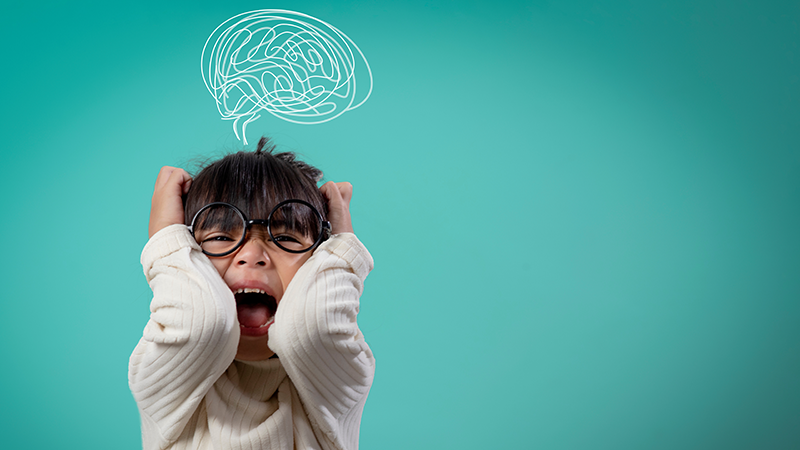WISC-Ⅴとは?WISC-Ⅳとの違いと結果の見方を徹底解説

「受けた検査がWISC-IVだったけど、古い?Ⅴじゃなくて大丈夫?」
「WISC-Ⅴが最新って聞いたけど、WISC-Ⅳと何が違うの?」
WISC検査は、学校や発達支援センター、児童相談所などで実施されることが増えているので、「WISC-Vが最新版」と聞いて気になっている保護者の方も多いと思います。
そこで、
- WISC-Vとはどんな検査なのか
- WISC-IVとの具体的な違い
- 検査結果をどう読み取り、支援や学習にどう活かせるのか
を詳しく解説します。
WISC-Vの指標や構成、結果の見方を正しく理解することで「お子さんの強みと課題」「日常や学習での困りごと」「支援方法の方向性」がより詳しくわかるようになります。ぜひ参考にしてみてくださいね。
『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
WISC検査とは

WISC検査(ウィスク検査)とは、5歳0か月〜16歳11か月のお子さんを対象とした知能検査です。
ウェクスラー児童用知能検査WISCの最新日本版で、正式名称は Wechsler Intelligence Scale for Children(ウェクスラー児童用知能検査)と言います。
学習の得意・不得意や、思考・理解・記憶・処理速度などの認知の特性を数値化し、発達支援や教育現場、臨床心理の分野で幅広く活用されています。
WISCは知能を「一つのIQ」としてではなく、複数の能力(言語理解・ワーキングメモリ・処理速度など)に分けて分析できる点が特徴です。そのため、発達特性の理解や支援方法の検討に非常に有効です。
よく誤解をされやすいのですが、WISC検査は発達障害かどうかを見るための検査ではありません。
WISCは、子どもの「得意な部分と苦手な部分」から「その子にとってより良い支援の手がかりを得る」ことを目的として行う検査です。発達障害かどうかについては、あくまで専門の医師による総合的な判断になります。
WISCは時代に合わせて改定され、日本では2022年に最新版のWISC-Ⅴをリリース。WISC-Ⅳから順次移行している段階です。そのため、地域や機関によっては「Ⅳを受ける場合」と「Ⅴを受ける場合」がありますが、どちらでも信頼性・妥当性の高い検査が行われます。
WISC-Ⅴで何が変わった?WISC-Ⅳとの違い

WISC-Ⅴで大きく変わったことは2つ。
① 指標の数が4つから5つに変更
② ワーキングメモリ(WMI)に視覚情報も追加
です。それぞれ解説します。
違い① 指標の数が4つから5つに変更
WISC-Ⅳでは、次の4つの指標で認知領域を測定します。
● 言語理解(VCI)
言葉を理解してどれくらい使えるか、推論できるか
● 知覚推理(PRI)
目で見たものをどのように使えるか
● ワーキングメモリ(WMI)
耳から聞いた情報をとっておき、どれくらい使うことができるか
● 処理速度(PSI)
単純な作業をすばやく正しくできるか
WISC-Ⅴでは、このうちの「知覚推理(PRI)」指標がなくなり、「視空間(VSI)」「流動性推理(FRI)」の2つに細分化されました。
WISC-Ⅳで測定する「初めて目にする情報から、適切な答えを推理する力」が、WISC-Ⅴでは「目にした物を理解する力」と「与えられた情報をもとに適切な答えを推理する力」という2つに変わったんです。
なぜ変わったのか。
それは、これまでのWISC‐Ⅳの知覚推理(PRI)の点数だけでは、その子が「目で見たものを理解するのが苦手」なのか、それとも「与えられた情報をもとに考えたり推理するのが苦手」なのか、はっきり分かりづらかったのです。
たとえば、空間認識(形や位置関係をつかむ力)はとても強いのに、「これからどうなるか」を予測するのが苦手なお子さんもいます。その場合、強みと弱みが打ち消し合ってPRIの点数が平均に見えてしまい、本来の得意分野に気づけないことも。
この問題がWISC-Ⅴよって改善され、お子さんの強みと弱みをより正確に測定できるようになったんです。

では、WISC-Ⅴ新しく追加された指標の視空間(VSI)と流動性推理(FRI)について解説します。
● 視空間(VSI)
「目で見た情報を正確に理解し、頭の中でイメージとして整理・操作できるか」を見る指標です。「見て処理する力」の土台となる重要な領域です。
たとえば、積み木の模様を見て同じ形を作る、図形を見て全体の構造を把握する、といった課題で測定されます。
VSIが高い子は、図や地図、立体構造を理解するのが得意で、絵や工作・パズルなどの活動で力を発揮します。VSIが低い場合、図形問題や空間をイメージする課題が苦手になりやすく、板書の写し間違いや図形問題への苦手意識につながることがあります。
WISC-Vでは、視空間を独立して評価することで「目で見た情報をどのように処理しているか」をより具体的に把握でき、学習の得意・不得意をより正確に分析できるようになりました。
● 流動性推理(FRI)
「見たことのない問題や物事を新しい方法で考えたり解くことができるか」を見る指標です。学習の応用力や創造的思考力を評価するうえで重要な領域です。
たとえば、数列や図形のパターンを見て共通点を推理する課題などで評価されます。
FRIが高い子は、論理的思考や問題解決に強く、未知の課題にも柔軟に対応できます。FRIが低いと、抽象的な課題や文章問題の理解に時間がかかることがあります。
WISC-Vで新たに導入されたこの指標により、子どもが「具体的な視覚処理は得意だが、推論は苦手」といった個性を見つけやすくなり、より適切な学習支援につなげることが可能になりました。
違い② ワーキングメモリ(WMI)に視覚情報も追加
ワーキングメモリ指標(WMI)とは「情報を一時的に記憶し、同時に処理・操作できるか」を見る指標です。単なる短期記憶ではなく、頭の中で考えながら使う記憶力です。
たとえば、先生の説明を聞きながらノートに書いたり、会話の流れを記憶しながら次の言葉を考えたりといった場面で働く力です。勉強・会話・日常生活すべての基盤となる重要な能力です。
WISC-Ⅳまでは、ワーキングメモリは「耳で聞いた情報を記憶・処理する力」を測定しているため、聴覚的記憶を中心に評価されているため、「聞いて覚える力」は測れますが「見て覚える力(視覚的記憶)」までは反映されませんでした。
WISC-Ⅴでは、耳で聞く力に加えて「目で見た情報を保持・処理する力」も測定できるようになり、より総合的な評価が可能になっています。これにより、聴覚型と視覚型の両方のワーキングメモリ特性を把握できるようになりました。
つまり「耳で聞くより、見て覚える方が得意」など、子どもの【記憶のタイプ】をより正確に分析できるんです。
さらに、WISC-Ⅴでは単に「記憶できる量」ではなく「情報をどう扱うか」「どの感覚から処理するのが得意か」まで見えるようになりました。スコアの組み合わせを見ることで、学び方や支援の方向性を具体的に考えることができます。
ワーキングメモリ指標が低いと、
- 話を聞きながらメモをするのが難しい
- 計算の途中で手順を忘れてしまう
- 置いた場所や片づけた場所を忘れてしまうため、失くし物が多い
- 家に出る前に必要なものを思い出せず忘れ物をしてしまう
といった困りごとにつながりやすいです。
これらは単なる「不注意」ではなく、情報を一時的に保持する容量の少なさが関係していることも多いんです。
支援のポイントは「覚え方を工夫する」ことです。口頭よりも視覚的な情報提示(メモ・図・手順カード)を使う、指示を一度に出さず、順を追って伝えるなどの工夫が有効です。
WISC-Vのワーキングメモリ指標(WMI)は、単に「記憶力」を測る検査ではなく、お子さんがどのように情報を理解・保持・使っているのかを明らかにする指標です。
この違いを知ることで、検査結果を「支援につなげるための実践的なヒント」として活かすことができます。
受けた検査がWISC-Ⅳでも大丈夫?

結論から言うと問題ありません。
確かに、最新版のWISC-Ⅴでは指標が4つから5つに増え、より細かく子どもの力を見られるようになりました。ですが「Ⅳで受けたから不利」「Ⅴじゃないと意味がない」ということはないんです。
大事なのは検査のバージョンではなく、そこから何を読み取り、どう支援につなげるか。
WISCはⅣでもⅤでも、お子さんの特性を知り、学び方のクセや得意・苦手を理解するための大切なツールです。
結果を手にすると、どうしても数値そのものに目がいきがちですが、本当に注目すべきなのは点数の高さではなく凹凸のバランス。そこから「お子さんに合った学び方のクセ」が見えてきます。
だからこそ、どちらの検査であっても「結果をどう活かして支援につなげていくか」という視点が一番大切です。
まとめ

WISC-Vは、単なる知能検査ではありません。
お子さんが「どんなふうに考え」「どのように学び」「何につまずきやすいのか」を見える化するためのツールです。
WISC-IVでは捉えきれなかった「視覚的な処理力」や「柔軟な思考力」「情報の扱い方」まで測れるようになったことで、WISC-Vはより今の子どもたちに寄り添った検査となりました。
検査結果は、点数の高さを競うものではなく「苦手を補う」「得意を伸ばす」ための具体的な手がかりとして活用しましょう。
もし、お子さんの検査結果を見て不安に感じたり「どう活かせばいいかわからない」と迷ったときは、専門機関(検査を実施している施設・医療機関等)に問い合わせてみることをお勧めします。
発達障害サポート資料
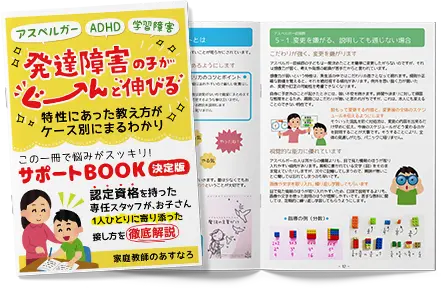
この資料でわかること
- 発達障害の子を伸ばす教育とは?
- 特性に合わせた具体的な教え方
- よくある困りごとと対応例 など
発達障害の専門家が監修!お子さんをぐーんと伸ばす接し方を徹底解説
この一冊で、特性ごとの勉強の悩みがスッキリ解消!
教え方に困った時にスグに対応できる!