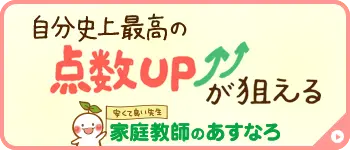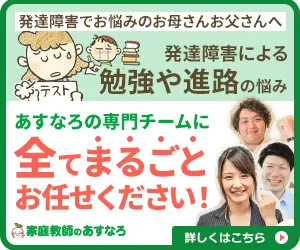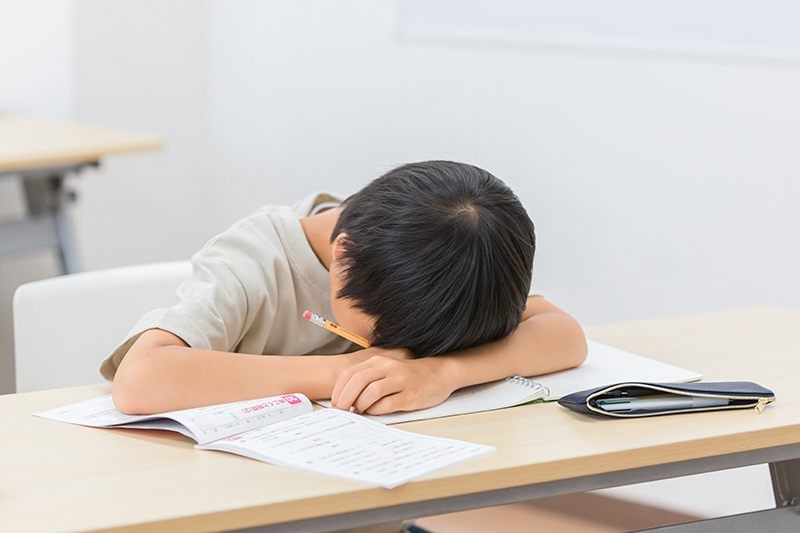宿題しないのはなぜ?発達障害の子に“合った”やり方を見つけよう
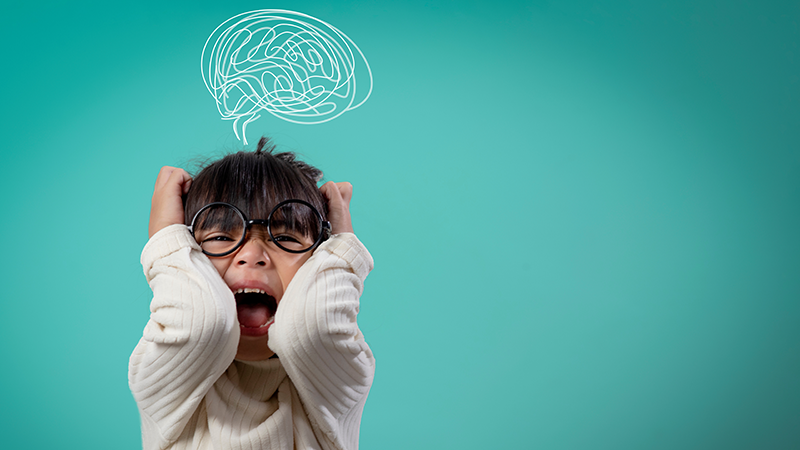
『勉強が苦手』な子専門で36年の家庭教師あすなろの体験授業を受けてみませんか?
あすなろでは、どこよりもお子さんの気持ちに寄り添い、勉強が苦手な子にとって最高の勉強法を教えています。
まずは、家庭教師のあすなろのホームページをご覧くださいね。
■「どうしてやらないの?」の前に、気持ちに寄り添ってみて
「また宿題やってない…」
「もう!何回言わせるの!」
「自分からやるのは無理なのかな…」
発達障害の子に限らず、宿題に向かえない子どもに、お母さんとしてはついイライラしてしまいますよね。
それは、「子どもにしっかりしてほしい」「困ってほしくない」という愛情の証なのですが、叱るだけでは不十分な場合があります。
実は、発達障害のあるお子さんの場合、「やらない」=「サボっている」ではないことがとても多く、「やりたくない」のではなく、「やれない」状態にいることもあります。
そこでこの記事では、発達障害のある子が宿題をしない本当の理由と、特性に合った対処法をご紹介します。
親御さん自身がラクになる考え方や方法もお伝えしますので、ぜひ最後まで読んで、家庭学習が苦にならない方法を見つけてくださいね。
■発達障害の子が、宿題を“しない”のではなく、“できない”4つの理由
発達障害のある子が宿題に取り組めない背景には、「怠け」や「反抗」ではなく、その子なりの困難さやつまずきがある場合がほとんどです。
見た目にはわかりにくくても、頭の中ではたくさんのハードルを感じていることがあります。
① 「何から始めていいか分からない」
たとえば、プリントが3枚あるときに「全部やっておいて」と言われると、どこから手をつければいいか分からなくなってしまうことがあります。
ASD傾向の子どもにとっては、「漠然とした指示」や「先の見えないタスク」は非常に取りかかりづらいものなのです。
解決ポイント
• 「1枚目の漢字から始めようね」と順番を示す
• 「まず○○、次に□□」など段階を具体的に伝える
• 見通しを持てるチェックリストを活用する
② 自信がなくて避けてしまう
「どうせ間違える」「できないって言われたらイヤだ」そんな気持ちから、あえて宿題から目をそらす子もいます。
過去に怒られた、友達より遅れていると感じた経験から、「宿題=怖いもの」「苦手な自分を見せる場所」になってしまっているのです。
解決ポイント
• 「できた部分」に目を向けて、細かく褒める
• 「間違えてもいいよ」「失敗しても大丈夫」と安心させる
• 小さく成功できるよう、量やレベルを調整する
③ 感覚過敏・疲労が影響している
学校から帰った後は、エネルギーがほとんど残っていない子も多くいます。
また、発達障害の子には感覚過敏がある場合もあり、「部屋の電気がまぶしい」「服のチクチクが気になる」「周りの音が気になって集中できない」といった困難がある子も多く、それが理由で集中できませんし、体力も使ってしまいます。
解決ポイント
• 照明を調整する、耳栓やイヤーマフを使うなどの環境整備
• 宿題前にリラックス時間(おやつ・音楽・静かな時間)を取る
• 「疲れている日は10分だけ」など柔軟に対応する
④ 環境や声かけが合っていない
「リビングでテレビがついている」「きょうだいが騒がしい」など、周囲の環境が集中に向かないこともあります。
さらに、きつい言い方や急かしすぎる声かけは、子どものやる気をさらに下げてしまい、モチベーションを失ってしまう場合も。
悪い声かけの例
• 「早くしなさい!」
• 「またサボってるの?」
• 「なんでできないの?」
解決ポイント
• 静かなスペースをつくる・整理整頓された机を用意する
• 「10分だけ一緒にやろうか」「どれからやりたい?」とやさしく声をかける
• できたときには「最後までがんばったね」とポジティブなフィードバックをする
良い声かけ例
• 「一緒に始めてみようか」
• 「今日はこれだけでOKだよ」
• 「やることが決まってると安心するよね」
• 「ここまでできたね、がんばった!」
肯定的で具体的、見通しが立つ声かけを意識してあげると、子どものやる気や安心感が育っていきます。
■発達特性別|宿題に向き合えない理由とサポートのやり方
【ASD(自閉スペクトラム症)タイプ】
ASDの子どもは、予測できないことや抽象的な指示に不安を感じやすく、「完璧にやらなきゃ」と思いすぎて動けなくなることがあります。また、細部にこだわりすぎて全体が進まないこともあります。
よくある困りごと
• 「どこまでやればいいの?」と見通しが立たないと手が止まる
• 「間違えたくない」と思いすぎて、1問に時間をかけすぎる
• 計画外のことが起きると混乱し、取り組む意欲がなくなる
具体的なサポートのヒント
●“今から何をするのか”を明確にする
→ ホワイトボードや紙に「①漢字プリント」「②算数ドリル1ページ」など、順序と量を視覚的に書き出す。
→ 「終わったらシールを貼る」など、見える進捗が安心感に。
● “1問完璧”より“5問ざっくり”を目指す
→ 完璧主義で止まってしまう場合は、「まず全問をざっくり解いてから、あとで見直そう」と段階を分ける提案を。
●予定変更には“予告”と“代替案”を
→ 「今日は宿題の順番を変えるよ」と事前に伝える+別の案を提示することで混乱を防ぐ。
●「完璧じゃなくてOK」な雰囲気づくり
→ 途中で終わっても「ここまでできたね」と声かけをして、“終わらせること”より“やる気を保つこと”を優先。
【ADHD(注意欠如・多動性障害)タイプ】
集中力が長く続きにくく、気が散りやすい傾向があります。また、時間の感覚が薄く、「やる気はあるのに行動できない」ことに本人もモヤモヤしている場合が多いです。
よくある困りごと
• 始めるまでに時間がかかり、気づけば夕方
• 座っていても手が動かず、別のことに意識が向いてしまう
• 宿題の途中で「飽きた」「疲れた」と離席する
具体的なサポートのヒント
●「5分だけモード」から入る
→ 「とりあえず5分だけやってみよう」を合言葉に。短時間×低ハードルでスタートする習慣を。
●視覚・聴覚の刺激を最小限に
→ テレビ・スマホ・本・おもちゃなどは視界から除去。静かな環境に切り替え、イヤーマフや仕切り板も有効。
●集中後の「即ごほうびルール」
→ 「10分宿題→10分YouTube」など、“やった直後に楽しいことが待っている”構造をつくると意欲UP。
● 立ってやってもOK、動きながらもOK
→ 体を揺らしたり、歩きながら音読するなど、“動ける環境”に変えると集中しやすい。
【LD(学習障害)タイプ】
学習の特定分野にだけ強い困難があり、本人の努力不足ではなく、脳の処理のしかたによるものです。「できない自分」を自覚して自己肯定感が下がっているケースも多くあります。
よくある困りごと
• 文章題を読めないので、何をすればいいのかわからない
• 一桁の計算はできるが、筆算になるとパニックに
• 何度も間違えて、「自分はバカなんだ」と思っている
具体的なサポートのヒント
●音読や説明は“一緒に”やるのが基本:
→ 苦手な部分(漢字・文章など)は保護者が代読し、“何をするかの理解”だけに集中させる。
●“1ページ終わらせる”より“できた感”を重視:
→ 「1問できたらOK」「今日のゴールは3分間だけ」など、量でなく質と達成感を大切に。
● 書く以外の手段も活用する:
→ タブレット、音声入力、指さし回答、口頭回答など、得意な方法でアウトプットできる工夫を。
● “できた部分”にしっかり光を当てる:
→ 間違いに目を向けるより、「この部分よく読めたね!」とプロセスの努力や挑戦自体を認める声かけを。
【どんな特性の子にも共通のヒント】
発達特性が異なっても、すべての子どもに共通して大切なことがあります。
●「できた体験」を積ませること
小さな「できた!」が、「自分にもできる」「またやってみよう」につながります。
● 「やらなきゃ」より「やってみたい」へ
強制感ではなく、「このやり方ならできそう」と思える工夫が、子どもにとっての“挑戦”を“安心”に変えます。
● 親は“監督”でなく“伴走者”に
叱るよりも、寄り添い、時には一緒に机に向かい、「ここまでやってみようか」と子どもの気持ちを受け止めながら進める姿勢が大切です。
■子どもの“やってみよう”を引き出す6つの工夫
「宿題しなさい」と言っても動かない…。
そんなときは、子どもが「ちょっとやってみようかな」と思える小さなきっかけを、親御さんが意識的につくってあげてください。
今日からできるやり方を紹介しておきます。
1. 視覚化できる「宿題リスト」を作る
チェック式のリストやホワイトボードを使って、「あとどれくらい」が見えるようにします。
終わったらシールを貼るなど、達成感を得られる仕掛けも効果的です。
2. 「10分だけ」タイマーで区切る
長時間の集中が苦手な子には、「10分だけ」が有効。
タイマーを使い、終わったらミニごほうびを用意するとやる気が出やすくなります。
3. 並んで取り組む・親も手を動かす
隣で親が本を読む、メモを書くなど、同じ空間で“やってる雰囲気”をつくると子どもも安心して取り組めます。
4. 遊びの要素を取り入れる
クイズ形式で出題したり、スタンプカードを作ったり、楽しく取り組める工夫を入れましょう。
5. 宿題前の“ウォーミングアップ”を習慣にする
いきなり始めるのではなく、「手洗い→お茶→スタート」などの流れを決めておくと切り替えやすくなります。
6. 自分で選ばせる「選択制」にする
「どれからやる?」「どこでやる?」など、選択肢を与えることで自主性が育ちます。
■お母さんがラクになることも、大切にして欲しいです。
毎日、宿題のことで悩んでいませんか?
宿題ひとつで怒鳴ってしまったり、泣きたくなったりする日もありますよね。
でも、それはお母さんが真剣に子どもに向き合っている証ですが、お母さんにもっと笑顔でラクな気持ちでいて欲しいんです。
「ちゃんとやらせなきゃ」よりも、「今日は無理しない」も選択肢に入れてください。それで大丈夫です。
▼ お母さんが少しラクになる5つの方法
1. 全部やらせようとしない
今日は1枚だけでOK!など、自分の基準をゆるめましょう。
2. 仕組みで声かけを減らす
タイマーやチェックリストで、毎回の声かけを減らせます。
3. 「やらない日」もOKにする
疲れている日は「おやすみ宣言」で心を軽く。
4. 愚痴を言える人を見つける
同じ立場の親とSNSでつながったり、支援機関に話すだけでも違います。
5. 自分へのごほうびタイムをつくる
子どもが宿題を終えたら、お母さんも紅茶やスマホでリフレッシュ!
焦らず、完璧を求めすぎず、お母さん自身がラクでいられる関わり方を大切にしていきましょう。
「できない」には理由がある。親子で少しずつ前へ
発達障害のある子どもが宿題に取り組めないのは、「やる気がない」からではなく、 『見えにくい困りごと』 や 『特性による“できない理由”』 があるからです。
だからこそ、叱るのではなく、お子さんの特性に合った方法で寄り添いながら、「やってみようかな」と思える工夫や関わり方を見つけていって欲しいのです。
そして、お子さんの宿題に悩みすぎて、お母さん自身が疲れ切ってしまわないようにしてください。完璧じゃなくて大丈夫。
焦らず、親子で一緒に少しずつ、 「この子に合ったやり方」 を見つけていきましょう。
発達障害サポート資料
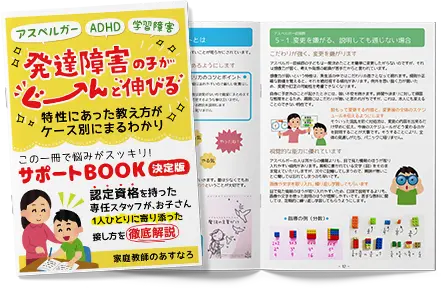
この資料でわかること
- 発達障害の子を伸ばす教育とは?
- 特性に合わせた具体的な教え方
- よくある困りごとと対応例 など
発達障害の専門家が監修!お子さんをぐーんと伸ばす接し方を徹底解説
この一冊で、特性ごとの勉強の悩みがスッキリ解消!
教え方に困った時にスグに対応できる!