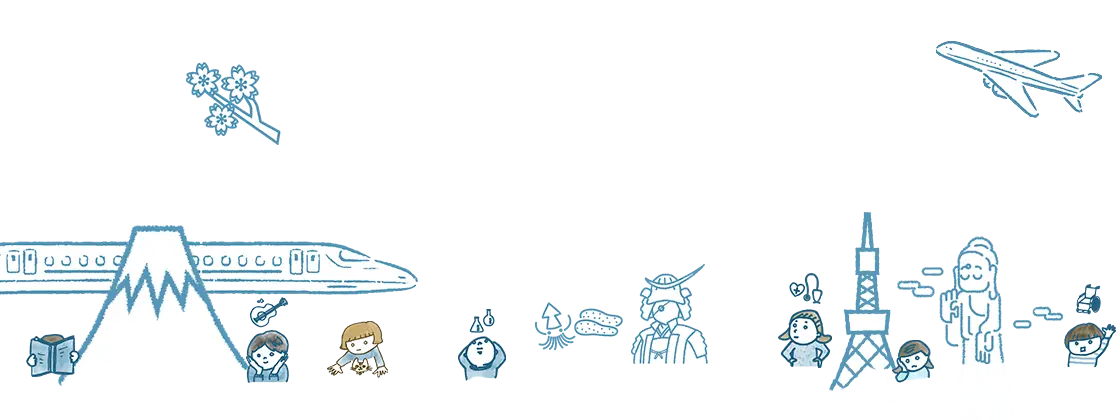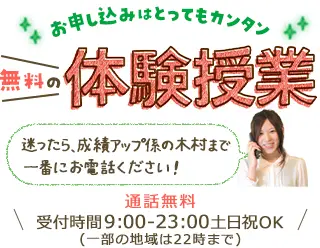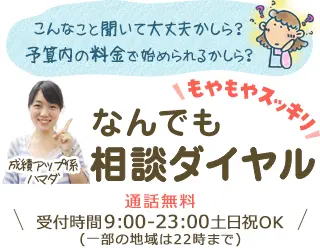沖縄県立高校入試情報
2026年度 沖縄県立高校入試情報
特色選抜
| 出願 | 2026年2月2日(月)、3日(火) |
|---|---|
| 検査日 | 2026年3月4日(水)、5日(木)*1 |
| 合格発表 | 2025年3月17日(火) |
- *1 各学校の募集要項参照
一般選抜
| 出願 | 2026年2月2日(月)、3日(火) |
|---|---|
| 志願変更申し出 | 2026年2月6日(金)、9日(月) |
| 志願変更願書取り下げ・再出願 | 2026年2月16日(月)、17日(火) |
| 学力検査・面接等 | 2026年3月4日(水)、5日(木)*1 |
| 合格発表 | 2026年3月17日(火) |
- *1:第1日目国語・理科・英語 第2日目社会・数学
詳細情報
- 追検査について
-
・申し出期間:2026年3月4日(水)及び5日(木)
・追検査日:2026年3月9日(月)
第2次募集
| 出願 | 2026年3月18日(水)、19日(木) |
|---|---|
| 志願変更再出願 | 2026年3月23日(月) |
| 検査日 | 各学校の募集要項参照 |
| 合格発表 | 2026年3月27日(金) |
- 合格者が募集定員に満たない学科・コースにおいて、第2次募集を行う
前年度の入試問題出題内容の分析と効果的な学習方法
※本記事は自治体の資料をもとに作成していますが、配点や問題内容の正確な情報は必ず各自治体の公式サイトでご確認ください。
- 英語
- 数学
- 国語
- 理科
- 社会
英語
| 範囲 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| リスニング【大問1】~【大問3】 | 会話分の内容把握、応答、質問の答え(選択式) | 9点 |
| 基本的な文法【大問4】~【大問7】 | 英文穴埋め・並べ替え(選択式・記述) | 20点 |
| 読解 | 資料読解(選択式) | 5点 |
| 読解 | スピーチ文(選択式) | 7点 |
| 長文読解 | 授業で発表する原稿(選択式・英作文) | 13点 |
| 英作文 | 資料から読み取り自分の意見を20語以上で記述 | 6点 |
学習ポイント
- 出題の分析 その1
- 基礎問題について
- 効果的な学習方法
-
問題数多めで配点が低い。基礎問題を確実に取りましょう。
基礎問題とは:教科書で必ず習い、ワークや確認テストで繰り返し出るレベルの文法・単語・会話表現のこと
例えば:
文法・語法の基本
・動詞の時制(過去形・現在完了・未来)
・三単現の s、be動詞と一般動詞の区別
・助動詞(can, must, will など)の基本用法
・比較級・最上級
・不定詞・動名詞(to+動詞 / 動詞+ing)の使い分け
数学
| 範囲 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 小問集合【大問1】【大問2】 | 計算の基礎・一次・二次・根号・図形・データ・確率 | 24点 |
| 箱ひげ図・統計読解 | 計算・選択 | 4点 |
| 確率 | 計算 | 4点 |
| 一次規則性 | 一次関数・等差数列的な関係(計算) | 4点 |
| 作図 | 根拠線(作業痕)と中心Pの記号を明示すること | 1点 |
| 関数:二次関数×直線×面積・会話型 | 空欄補充 | 5点 |
| 平面図形:円・相似・長さ・面積 | 計算・証明 | 6点 |
| 立体:立方体の体積・点移動・断面の高さ | 計算 | 6点 |
| 数の規則性:三角配列と総和・説明 | 計算・説明 | 6点 |
学習ポイント
- 出題の分析 その1
- 問題構成について
- 効果的な学習方法
-
大問1・2で「計算・方程式・資料・確率」などを小問形式で次々出す
大問3以降も関数・作図・証明・規則性と、科目全範囲をまんべんなく出題されている
1問1問の配点は低いので、ケアレスミスを防ぎながらテンポよく解く力が必要。
得点戦略としては「基礎小問を確実に拾い、時間を残して作図・証明に取り組む」ことが重要です。
国語
| 範囲 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 文学的文章(随筆) | 内容理解・漢字の読み書き(選択式・短い記述) | 16点 |
| 評論文(説明的文章) | 内容理解(選択式・短い記述) | 17点 |
| 古文 | 基本文法・内容理解(記述・選択) | 8点 |
| 漢文 | 基本句法・内容理解(記述・選択) | 5点 |
| 資料読解+会話文を使った思考力問題 | 探究型・対話型問題(選択・記述) | 14点 |
学習ポイント
- 出題の分析 その1
- 探究型・対話型問題
- 効果的な学習方法
-
実際の文章やデータを読み取るだけでなく、生徒同士の会話を通して「どう考えるか」を問う形式。
①正解は本文に書いてある」ではなく「会話を整理する」力
登場人物が資料をどう理解したか/どう意見を述べたか をたどる必要がある。
②会話の流れを読む力
単なる暗記型ではなく、対話の展開を追う力を養うことがポイント
③自分が参加しているつもりで読む
生徒たちの会話は「受験生に考えさせたい視点」を代弁している場合が多い
もし自分がその会話に加わるなら、どう意見を言うか?という意識で読むと理解しやすい。
文章を「第三者的に分析する」のではなく、会話に入り込む読解が求められる。
④単純に「グラフから○○を読み取る」問題ではなく、「Aさんの解釈は適切か?」「Bさんの意見の根拠はどこか?」を見抜く力が必要。
「資料を読む」→「会話を通して検証する」 という二段階処理が学習ポイント。
理科
| 範囲 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 地学分野 | 地震の発生と揺れの伝わりについて・グラフ読み取り(記述・選択) | 7点 |
| 化学分野 | 物質の密度の実験から(記述・選択) | 7点 |
| 物理分野 | コイルと磁界の実験から(選択・記述・説明文記述) | 8点 |
| 生物分野 | 刺激と反応・神経、反応の実験(選択・記述・説明文記述) | 7点 |
| 化学分野 | 化学変化と物質の性質の実験(選択・記述・説明文記述) | 8点 |
| 天体分野 | 月の動きと日食・月食(選択・記述) | 8点 |
| 生物分野 | 進化と比較解剖(選択・記述・説明文記述) | 8点 |
| 物理分野 | 斜面上の運動と力学的エネルギーの実験(選択・記述・説明文記述) | 7点 |
学習ポイント
- 出題の分析 その1
- 全分野共通
- 効果的な学習方法
-
①用語暗記+「実験手順の意味」
結論でなく手順の理由と結果の対応を言葉で説明できるように
②グラフ・図の「型」認識
③短い説明で加点を取り切る
④現象↔数式↔言葉 - 出題の分析 その2
- 天体・地学について
- 効果的な学習方法
-
「配置」で考える
月の満ち欠け/日食・月食は太陽‐地球‐月の並びを図で即描けるよう練習。地震は震央距離と到達時刻差の読み取りを反復
社会
| 範囲 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 世界地理 | 世界の気候帯・海流・農作業など資料、グラフ、写真読み取り(選択・記述・説明文記述) | 10点 |
| 日本地理 | 産業・人口密度など資料、地形図、グラフ読み取り(選択・記述) | 10点 |
| 歴史(~近世) | 世界と日本の歴史上のできごと比較、年表、地図、写真読み取り(選択・記述) | 10点 |
| 歴史(近世~現代) | 産業革命・帝国主義・条約改正・選挙制度など(選択・記述・並べ替え) | 10点 |
| 公民(政治のしくみ・選挙・情報) | 三権と国民の関わり・選挙区の人口の問題・メディア・情報リテラシー(選択・記述・説明的記述) | 10点 |
| 公民(消費生活・労働・金融・社会保障・エネルギー) | 売買契約・物価・為替・社会保障・エネルギー等(選択・記述) | 10点 |
学習ポイント
- 出題の分析 その1
- 満遍なく出題されることへの学習ポイント
- 効果的な学習方法
-
全分野を「穴なく仕上げる」
「基礎知識+資料読解」の二本立て
単語暗記だけではなく、グラフや表を読み取り、自分の知識と照合する力が必須。
横断的に考える力をつける
・歴史+地理(例:産業革命→都市化→人口ピラミッド)
・公民+社会問題(例:高齢化→社会保障→税制)
・単独分野の暗記にとどまらず、分野をまたぐ因果関係を意識すると得点安定につながる。
家庭教師あすなろ
指導エリア
指導エリア